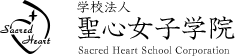シスター・先生から(宗教朝礼)
2018.02.28
2018年2月28日放送の宗教朝礼から
これから宗教朝礼を始めます。
まもなく2017年度が終わろうとしています。今年もいろいろな本や人との出会いがありました。
この1年間に読んだ本の中で最も心に残った本は若松英輔によって書かれた、カトリックの思想家、吉満義彦の評伝(『吉満義彦』)でした。
この本の中に吉満義彦について書かれた「吉満先生のこと」という遠藤周作のエッセイが紹介されています。その一節を引用します。
先生の机には若い、うつくしい女性の写真がおかれてあった。それは先生の若い頃、亡くなられた婚約者の写真だと寮生の一人が教えてくれた。この婚約者の女性は結核で早く亡くなられたが、臨終の時、先生は司祭をよんで二人だけの結婚式をあげられ、以来、先生は独身を守られたのである。
妻を失って大きな悲しみの中にいる吉満を一人にしてはならないと考えたのが、不二聖心の前身である温情舎の校長を務めた岩下壮一でした。岩下は、ある日、吉満を日光への旅に誘います。この旅の途上で岩下は吉満に、東京信濃町のカトリックの学生寮で若者の指導にあたる立場に立ってはどうかと持ちかけます。これもまた吉満を一人にしてはならないという配慮からでした。吉満が寮の指導者となってしばらくして入寮してきたのが作家の遠藤周作でした。吉満は遠藤の将来を真剣に気遣い、作家遠藤周作の誕生につながる助言をしていきます。
1933年に吉満義彦が経験した妻の死は彼の後の生涯に大きな影響を与えました。次に引用するのは妻の死後に吉満が書いたエッセイです。
私は自ら親しき者を失って、この者が永久に消去されたとはいかにしても考え得られなかった。否な、その者ひとたび見えざる世界にうつされて以来、私には見えざる世界の実在がいよいよ具体的に確証されたごとく感ずる。最も抽象的観念的に思われたであろうものが最も具体的に最も実在的に思われてきた。
妻の死によって、目には見えない世界の実在を確信した吉満の哲学者としての生涯は、その後、いっそうの深まりを見せていき、彼は著述や大学での講義にさらに力を入れていきます。熱情をもって語られた言葉は、それを受け取った者の魂の中で生き続けると信じていた彼は命を削るほどの努力をして講義の準備に取り組みます。その結果、吉満は健康を害してしまいました。次に彼の親友、木村太郎が1945年に書いた文章を引用しましょう。
彼は自分で聖トマス・アクィナスの『神学大全』に取組んでいった。上智のクルトゥル・ハイムでやった『神学大全』の講義は吉満としては彼の生涯の中で一番一生懸命の仕事だったように私は感じた。例の調子で、大したことはないようには言っていたが、この時の努力はかなり彼の健康を損なったようである。それからあと、だんだん彼の健康は衰えていって、到頭ほんとうに寝込んでしまったのだ。
このあと吉満の病は恢復することがありませんでした。命を削るようにして授業準備に取り組み健康を害して死んで行った吉満義彦の講義への情熱と学生への愛に強く心を打たれました。この事実は親友の木村太郎がいたからこそ記録として世に残ったわけですが、その記録者が不二聖心女子学院の校歌の作詞者であることにも深い感銘をおぼえました。木村太郎もまた吉満義彦の近くにいて、実在の秩序を信じる信仰心の影響を受け、この世の真理に目を見開かれていったのではないかと思います。「よき日給いし主を讃めん」という不二聖心の校歌の一節には木村太郎という一人の文学者の人生の経験の深まりが反映されているように思えてなりません。
これまで吉満義彦、岩下壮一、遠藤周作、木村太郎といった名前を挙げてきました。これらのすべての人物とつながる野村英夫という詩人がいます。野村英夫がカトリックの洗礼を受けた時に代父を務めたのが吉満義彦であり、堅信の時の代父が木村太郎でした。遠藤周作は「モジリアニの少年」という野村英夫についての、愛情のこもったエッセイを書いています。最後に野村英夫の「瞬く星」という詩を引用しましょう。
瞬く星 野村英夫
私はこのやうな一ときを愛するだらう
古びた鳩時計の音に
私がふと夜更けて夢から眼覚め
閉ざし忘れられた窓から
瞬く星と暗い闇と永遠との中で
対話するような一ときを
だが私はさらに愛するだらう
昨夜まで異邦の神々のやうに
瞬いて見えたそれらの星が
あたかも祭壇の前に跪いた少女達のやうに
今始めて全能者の大きな秩序の中に
つつましく瞬くのを見知つたやうな
大きな驚きに満たされたそんな一ときを
不二聖心女子学院と何らかのつながりを持つ、吉満義彦も岩下壮一も木村太郎も野村英夫も同じことを大切にしていました。それは、目に見える世界だけが唯一の世界ではなく、それとは別に目には見えない世界があり、その世界から聞こえてくる「愛の行為にまさるものはない」という声に私達は応えていかなければならないという思いでした。不二聖心で生活する私たちもまた、同じ声によって招かれていることを思い起こしてこの一年を終えられたらと思います。
これで宗教朝礼を終わります。
H.M.(国語科・宗教科)