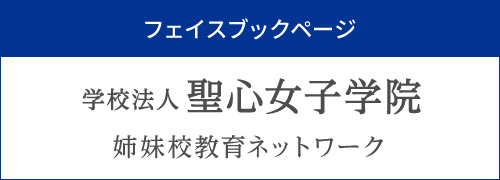不二聖心からのお知らせ

2025.10.08
2025年10月8日放送の宗教朝礼から
今年は戦後何年ですか? そう、80年です。私の母は1941年生まれ、今年84歳になります。太平洋戦争が始まった年の生まれです。戦争中の記憶はほとんどなく、母の昔話は終戦後のことがほとんどです。母が生まれたころ、一家は東京に暮らしていたそうです。父親は小学校の教員でした。
戦争が始まり、戦火を逃れて実家のある沼津に疎開し、そのまま沼津で過ごしました。母の兄弟は姉が2人、弟が一人の4人兄弟でした。娘3人は現在、92歳、88歳と二人とも元気に暮らしています。弟は、終戦の4年後、1949年に疫痢という病気で亡くなりました。4歳でした。
疫痢というのは、赤痢菌が腸に感染することが原因で起こる感染症です。赤痢菌が混入した食べ物や飲み物を食べたり飲んだりして感染するそうで、疫痢は小児にみられる細菌性赤痢の重症型で、循環不全(血圧の低下、意識障害など)などを起こし、短期間に死亡するそうなのです。
当時、赤痢や疫痢で亡くなる人が多かったと言います。衛生状況が現在とは違いますから、感染も広がりやすかったのでしょう。感染経路は一番上の姉からでした。その時、別の病気のため入院していた姉(私にとっての伯母)が知らないうちに病院内で、赤痢に感染してしまっていました。現在なら、院内感染と言われて大きな問題になる事案でしょう。伯母の感染はお見舞いの後に分かりました。帰宅して数日で母と弟も発症し、幼かった弟はあっという間に容態が悪化したと言います。父親の友人の医師に診ていただき、天井からリンゲルという当時高かった薬を点滴していたことを母は覚えていると言います。残念ながら、治療は間に合いませんでした。自宅では母も赤痢になってしまい、入院・隔離が必要な状態でした。
みなさんもご家族を亡くした経験をもつ人もいるでしょう。葬儀を行うために、さまざまな準備が必要です。このとき、祖父母は初めての男の子として大切に育てていた息子の葬儀を行わなければなりませんでした。その上、1番上の娘は入院中、3番目の娘(母)を入院させる必要がありました。祖父は沼津市今沢というJR片浜駅近くから、清水町長沢にある国立病院(現在の静岡医療センター)まで母を連れて行くことになりました。距離は8キロです。母も具合が悪くなっているので歩いてはいけません。どうやって、祖父は母を病院へ連れて行ったのでしょう? タクシー?救急車? まだそのようなインフラは整備されていませんでした。自家用車も普及していません。(祖父は生涯運転免許をもたず、移動は専ら自転車でした) 荷車に布団を敷いて、母を乗せて8キロの道を進んだのです。荷車って何?と思う人もいるでしょう。リヤカーは分かりますか?荷物を運ぶために金属製のパイプと空気入りタイヤで構成された2輪の荷車で、人もしくは自転車、オートバイによって牽引して使われます。リヤカーと違うのはタイヤ部分です。リヤカーは車輪がタイヤでできています。自転車のホイールと同じような構造。荷車はもっと古い形で、木の車輪を保護するために鉄の輪がついているものだそうです。道路の舗装はありません。でこぼこの道をクッションもない荷車に母を乗せて、亡くなった息子を自宅に置いて祖父は出かけました。帰りも空になった荷車を引いて、自宅に戻りました。3~4時間かかったのではないかと想像します。
お葬式を行うためにはお金が必要です。荼毘に付したりするためですが、祖父母にはそのお金がなかったと言います。祖父は自宅に戻ると、沼津駅へ向かい、闇市で自分の革靴を売りに行ったのだそうです。5キロの距離を歩いて往復。当時、駅の前、今のバスターミナル、西武百貨店のあたりに闇市があったのだそうです。沼津駅を知っているみなさん、70~80年前は空襲によって駅付近も多くの建物が焼失し、闇市もあったことを想像してみてください。子どものお葬式を行うために、お金になりそうなものとして革靴を売るということから、当時の生活が決して楽ではなかったことがうかがわれます。
一方、祖母は裁縫も得意でした。母の弟は上3人が女の子であったので、普段は女の子の服をお下がりで着ていたそうです。外出するときのために1着だけ男の子の服が用意され、出かけるたびにそれに着替えていたそうです。亡くなった息子のために着せる着物も、もちろんありませんでした。祖母はせめて男物の着物を着せてやりたいと、夫の着物をほどき、子どもの着物になるよう布を裁ち、一晩かけて着物を縫ったのだそうです。祖母の気持ちはどんなであったか?想像するだにつらく悲しいものです。
弟の葬儀には、母は参列することはできませんでした。約20日間の入院の後、退院して自宅に戻ったとき、母親から「大切な息子ではなく、娘が残った」という意味の、心ない言葉をかけられたそうです。小学2年生の女の子に、子どもを失った親の悲しみを受けとめる力はありません。この言葉は母の心に深い傷となりました。年齢も兄弟の中で最も近く、一緒に遊ぶことの多かった弟を失った母自身の悲しみもあったはずです。弟の死は、その後家族の中でタブーとなっていったと言います。
これは市井のある家庭の物語です。でも、みなさんのおじいさま、おばあさま、ひいおじいさま、ひいおばあさまにも大なり小なり戦中・戦後を生きてきた物語があるはずです。語らない方もいらっしゃるでしょう。でも、お話を聞ける人は是非、お聞きしてみてください。あなたの身近な人のお話は、きっと訴えるものを持っているはずです。
各地で紛争はあるけれど第二次世界大戦のような大きなものは過去のものであり、その記憶を忘れてはならないーー10年くらい前までなら、私はそう思っていました。でも今は違います。過去の記憶が、現在に重なります。世界の状況を考えると戦争は新しい形となって、深刻さも比較にならないほどになっています。無人機やドローンによる攻撃、ミサイルの正確な爆撃、ガザの飢餓で痩せ細った人々、ジェノサイトと認定されても改善されることない現実、ーーそれらを私たちはほぼリアルタイムで知ることができます。音・映像によって。一方でイスラエル・ガザ、ウクライナ・ロシア、それぞれの立場の人々の声も知ることができ、憎しみの連鎖、立場の違いから来る考えや思いの乖離があって、現実の複雑性を如実に語っています。
平和への道は険しいけれど、私たちは知ること・思いを寄せることを忘れてはならないと思います。今年は希望の聖年。「希望」を心に、昨日始業式で蒔苗先生がお話しくださった映画『長崎―閃光の影で―』に出てくる看護学生の言葉「まっすぐ生きたい」という道を探していきましょう。
M.H.(国語科)