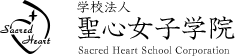フィールド日記
2016.12.20
烏瓜(カラスウリ)
東名高速沿いの裏道に烏瓜(カラスウリ)がたくさん実をつけている場所があります。夏目漱石が詠んだ句に、「世は貧し夕日破垣烏瓜」という句があります。漱石のつつましやかな庶民の暮らしに寄せる同情が伝わってくる句です。漱石という人は、小さいもの、弱いものに対して優しい心を向けた人でした。
今日のことば
今年も岩波書店は数々の名作を岩波文庫の一冊として世に送り出しました。その中でもとりわけ読み応えのある一冊が十川信介編『漱石追想』です。『漱石追想』には、漱石の同級生、留学仲間、教え子、同僚、文学者、編集者など、いろいろな立場で漱石と関わった人達が漱石を追想した文章が四十九編収められています。漱石を知る上で貴重な資料となり得る文章も多く、意外な発見に満ちた一冊となっています。例えば「腕白時代の夏目君」(篠本二郎)には少年の頃の漱石についての次のような一節があります。
夏目君が、牛込薬王寺前町の小学校より、学校帰り余の家に立寄るには、麹坂を登りて来るを常とした。又帰宅の時は焼餅坂を下りて帰った。然るに麹坂の麹屋に一人の悪太郎が居り、焼餅坂の桝本と云う酒屋にも亦悪太郎が居って、尚お之等の悪太郎を率ゆるに、鍛冶屋の息子で余等より四つ五つ年上なる大将が居た。夏目君はいつも彼等の為め種々な方法で苛めらるるから、何時か余と協力してこの町屋の大将を懲らしてやろうではないかと相談を持ち掛けた。この時代はまだ士族の勢力が盛んで、町人の子供は一般に士族の子供に対して恐れを抱いて居た。然し夏目君が学校帰り素手で四、五の町人の子供に苛めらるるのであるから、その内総大将を一人懲らせば後日の憂なかるべしとの考えで、その機会の来るのを待って居た。或時夏目君と余は余の屋敷の裏門で遊び居れる時、かの鍛冶屋の悪太郎が独り、余等の遊べる方向に歩行し来れることを遥かに認めた。余等は好機逸すべからずとなし、余は家内にかけ込みて何の分別もなく先ず短刀二振りを持来りて、その一を夏目君に与えたる時は、已(すで)に悪太郎は十四、五間の距離まで近づき来った。当時武士の斬り棄て御免とか云う無上の権威が、猶お町人やその子供の頭に残れる時分であったから、武士の子供が短刀一本さえ携え居れば、年長の町家の子供四、五人を相手に喧嘩して、終に逐(お)い散らして勝利を収むることが出来たのである。彼が余等に接近するや否や、余等は短刀を抜き放ちて彼の前後より迫った。彼は忽ち顔面蒼白となり、隙あれば虎口より脱せんとし、又近き小路の門内に入りて人の助けを乞わんとする態度にて、ぐずぐず言訳を唱えながら、二人に囲まれつつ次第に小路の中に退却した。彼が小路に入るや夏目君は手早く短刀を鞘に収めて、悪太郎に飛び付きて、双手にて胸元を押えて、杉垣根に彼を圧し付けた。悪太郎は年齢が余等より四つも五つも違い、腕力も余等二人協力しても及ぶ所ではなかったが、時代思潮上士族を恐れしと、余が白刃を持てるとによりて、夏目君の引廻わす儘に扱われて豪も抵抗しなかったのは、当時極めて愉快であった。夏目君は愈々彼を杉垣根に圧し付けて、彼の身体が側面より認められぬ程にし、余はこの動作中短刀を彼の胸元へつきつけて、夏目君と共に彼を殺して仕舞うと威嚇して居た。
このような文章を読むと漱石が明治時代の文豪であるとともに、江戸時代の遺風を実際に肌で感じて成長した人物であったことがわかります。
江戸人漱石を感じさせる一節をもう一箇所引用しましょう。
当時余の伯父に、今は故人になったが、いたずらなる人があった。余の夏目君と親しくせるを知りて、或時こんなことを余に話した。夏目の祖先は、甲斐の信玄の有力なる旗本であったが、信玄の重臣某が徳川家に内通せし時、共にあずかりて徳川家の家臣となったのだ。(中略)重臣の謀反さえなければ武田家の運命も今少しは続きしならんと、真か偽か、余が耳には親友の祖先に関することで、極めて異様に感じた。然し当分は質(ただ)すも気の毒で、夏目君には何にもこの事に就きて言わなかった。或時大喧嘩を始め、口論も尽きて已に腕力に訴えんとせし時、手近かなこの事実を語りて嘲った。夏目君は俄に色を変じて引別れ、逃ぐるが如く立去ったことがある。その後も再び仲直りをして常の如く遊びしが、喧嘩の場合、この事が一番同君をへこますに有効であったから、その後も折々この策を応用した。今更思えば小供心とはいえ、余の行の卑劣なりしを感ずると同時に、夏目君の廉恥を重ずる念の深かりしを感ずるのである。
漱石という人が「廉恥を重ずる念の深かりし」人物であったことは、『漱石追想』のさまざまな文章が伝えています。しかし、一方で少年時代の彼は、そのような漱石のイメージからは考えられないような悪戯をする少年であったことも、「腕白時代の夏目君」の次のような一節を読むとわかります。
余等は当時の子供のあらゆる悪戯を仕尽したる中に、極めて面白く思い、今もその時の光景を思い出しては、私(ひそ)かに微笑を浮べることがある。毎日午後の四時頃に、余が邸の板塀の外を二十二、三歳位な按摩が、杖をつき笛を吹きて通過した。此奴(こやつ)盲人に似ず活発で、よく余等を悪罵し、時に杖を打振りて、喜んで余等を逐い廻わした。余等も折々土塊など打付けて、彼を怒らした。或時学校で夏目君と一つ按摩を嬲(なぶ)ってやろうと色々に協議した。併し何時も矢鱈(やたら)に杖を振り廻すから、容易にその側に寄る訳にはいかぬ。そこで或時二人して、恰も按摩が塀の外を通過する頃、塀に登りて、一人は長き釣竿の糸の先きに付せる鉤に紙屑をかけ、一人は肥柄杓に小便を盛りて塀の上に持ち上げて、按摩の通過を待つ程に、時刻を違えずやって来た。
このあと二人は信じられないことをします。あの漱石が少年時代にどのような悪戯をしていたのか、本を手にとり、確かめてみてください。
掲載されている文章の内容はさまざまですが、漱石の人柄の温かさを伝える文章が最も多いように思います。例えば菊池寛は「先生と我等」の中で、「夏目さんには温情があると誰かが云ったが本当だね」という芥川龍之介の言葉を紹介しています。
漱石の温情を伝える具体的なエピソードを記した文章としては、鈴木三重吉の「漱石先生の書簡」が最も印象に残ります。その前半部分を引用します。
いつの年の冬のことであったか、たしか或雪どけの日に、南町のお家へ伺うと、先生は茶の間の縁側にこごんで、十二、三ぐらい? うすぎたない着物を着た、そこいら近所の子どもらしい少年に、英語の第一リーダーを教えていられた。先生は、胃がいたいと見えて、元気のない顔をしていられたが、でも、語気や態度には、ちっとも面倒くさそうな容子(ようす)もなく、丁寧に、訳解してやっていられた。少年がかえってから、どこの子ですと聞くと
「どこの子だか、英語をおしえてくれと言ってやって来たのだ。私はいそがしい人間だから今日一度だけなら教えて上げよう。一たいだれが私のところへ習いにいけと言ったのかと聞くと、あなたはエライ人だというから英語も知ってるだろうと思って来たんだと言ってた。」
先生はこういう意味のことを答えて微笑していられた。