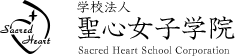フィールド日記
2013.01.08
ビワの花の送粉者は誰か

2013.01.08 Tuesday
高3の教室脇のビワの木が花をつけています。先日、この花を目にした時にこの寒い時期に咲く花の送粉者はいったい誰なのだろうと不思議に思いました。寒さに強い双翅目の昆虫もさすがに数を減らしています。
高3の担任をした時に、毎日眺めていたビワの実が、ある日、サルに食べられてがっかりしたのを覚えています。そのことを思い出してみても結実することは間違いないわけです。ならば送粉者は誰か。
その謎が今朝、解けました。たくさんのメジロが蜜を吸っていたのです。小鳥の存在をすっかり忘れていました。ビワの実はメジロが好む成分を多く含むように進化してきたという説もあるようです。
今日のことば
昨日の新聞から285 平成二十五年一月七日(月)
『レインツリーの国』(有川浩・新潮文庫)を読む
―― ひとみが伸行と会うのをかたくなに拒んだ理由とは ――
年末に近くの書店に行ったら、文庫の棚に「今、読みたい新潮文庫」のアンケートでベストテン入りした本が並べられていました。その中の第2位の本に先ず目がいきました。その本とは有川浩の『レインツリーの国』です。「昨日の新聞から283」で紹介した『三匹のおっさん』の感動を思い出し、すぐに購入しました。
今、読みたい新潮文庫のランキングには時々、なぜ選ばれたのか首をかしげたくなるような作品もあるのですが、今回は納得の第二位でした。一読して大きな感動を味わいました。『レインツリーの国』は文句なしの傑作です。
今週は、この『レインツリーの国』を紹介しましょう。
主人公の向坂伸行は、自分が大好きだったライトノベルの作品についてネット上である女性(ひとみ)が批評を書いているのを見つけ、そのサイトの管理者である女性(ひとみ)にメールを送ります。そのあたりの箇所を先ず引用してみましょう。
一体何の拍子でそんなことを調べてみようと思ったのかは自分でも分からない。
後から思えばそれが運命だったのかな、なんて思う。
大学を卒業し、関西から上京して入社三年目――東京にも仕事にも少しは慣れて、余裕が出てきたことがそんなものを思い出させたのかもしれない。
中学生のころに読んだライトノベルのシリーズ。実家に戻れば「捨てるな」と厳命してきた蔵書の中に背表紙が日に灼けて色が抜けたその文庫本は眠っているはずだが、今でもその出版社からその本が出ているかどうかは知らない。何しろ十年以上も前の本だ。
当時は読書好きな友達がいなかったので、その本の感想を話す相手はいなかった。ただその結末を呆然と受け止めて、――ちょっとしたトラウマになった。
その後もそのシリーズを何度となく読み返した。だが完結巻だけは滅多に読み返せなかった。
俺以外の奴は、あのラストをどう受け止めてたんだろう?
今更本当にどうでもいいことだ。本当にどうでもいいことをふと思い出して調べてみる気になった。それはやっぱり運命だったのかもしれない。
思いついたのが一年早くても一年遅くても駄目だった。その年でなければ。
そのときでなければ。
とにかくその夜、向坂伸行は初ボーナスで買って三年目のノートパソコンで、そのライトノベルのタイトルを検索したのである。
(中略)
その感想を見つけたのは検索結果を何ページか送った後である。
『……私にとっては忘れられない本です。
滑り出しはハチャメチャなSFアクション、しかも主人公たちは当時高校生の私と同じ高校生。おばかで開けっぴろげで同じクラスにいそうなフツーの男の子たち。
それが特殊工作員顔負けの大活躍! 謎の組織にさらわれたヒロインを取り返そうと敵地へ乗り込んで、ハチャメチャのムチャクチャを繰り返し、ついには取り返してハッピーエンド。
そんな感じで明るく楽しく始まったこのシリーズに、最後の最後で打ちのめされるとは思ってもみませんでした。
今までのハチャメチャが通用しない。隙のない大人たちの包囲網でどんどん主人公たちが追い詰められていく展開に、息苦しいような閉塞感を覚えました。
何をどう抗っても状況が打開できない無力感が、読んでいる私にもじっとりと絡みついて。もしかしたら……と浮かぶ想像を打ち消しながらページをめくりました。
きっと、最後は何とかなる。何とかなってくれる。
けれど、最後に主人公カップルは決定的に引き裂かれたのです。しかも、ヒロインの決断によって。追手から逃げ回る生活をヒロイン自身が拒否したのです。
どこまでも二人で逃げよう、と訴える彼に、どこまで逃げたって変わらないよ、と彼女は首を振ります。一生逃げ続けるの? と。
そして彼を含むクラスメイトは日常へ戻り、彼女は一人非日常へ旅立ちました。
彼女がまるで最初から存在しなかったように日常は動いていく。お互いに好きで、二人とも生きているのに、もう二度と会えない。
物語はそこで終わります。
恐い物を見たように急いで本を閉じました。何の救いもない終わりでした。
この本を好きだった友達も、みんなショックを受けていた。きっと、あの当時この本を読んでいた人はみんなショックだったと思います。
もっと言ってしまえば、傷ついたと思います。
作者に裏切られたと怒っている人もいました。もう二度と読まないと。子供っぽい身勝手な怒りかもしれませんが、それほどまでにあのラストは当時の私たちには衝撃が大きかったのです。
私たちはこの作品が好きで、この作品を書いてくれた作者が好きで追いかけてきたのに、何で作者はこんなふうに私たちを傷つけたんだろう? きっと私たちはそんなふうに思っていたのです。
私たちの好意を拒否されたように思っていたのです。
その結末が悲しくて、作者に拒否されたことが悲しくて、大好きだったその作品はなかなか読み返せない本になりました。
作品の結末に疑問を感じていた伸行は、ラストに傷ついたと語るサイトの管理者にコメントを送り、返事をもらいます。ネット上でのやりとりがしばらく続き、伸行は、ラストのとらえ方だけではなく、ひとみの考え方・感じ方にも共感を覚える部分が非常に多いことに気付いていきます。伸行はひとみに会ってみたくてたまらなくなりました。勇気をもってその気持ちをひとみに伝えましたが、ひとみはかたくなにその提案を拒み続けます。何度か、気持ちを伝え続けようやく二人は会うことができましたが、なぜかネット上のようにコミュニケーションがうまく成立しません。伸行は徐々に戸惑いを隠せなくなっていきます。
映画を観ようという話になった時にも、ぎくしゃくした感じは続きます。
話題作のうえ雨だったので客がこちらに流れたのか、映画館は思いの外混んでいた。全席指定制のチケット売り場は窓口に長蛇の列が出来ている。
伸行たちの番が来たときは、字幕版で直近の上映回は全席売り切れになっていた。次の回までは三時間近くある。
吹き替え版ならまだ空いているという係員の説明に、伸行はひとみを振り向いた。
「吹き替えでもええ?」
投げた確認は一応のもので当然頷くと思っていたから、頭を振ったひとみに思わず怪訝な顔になった。
「え、でも……字幕やと次の回まで待たなあかんし。三時間くらいかかんで」
字幕にこだわるタイプがいることは理解しているが、こんな場合は譲ってくれてもと戸惑う。
「吹き替えでも内容は一緒やから」
「字幕じゃないなら別のがいいです」
別のと言われても、他に洋画ではあまりぱっとしたタイトルはない。
「なら邦画じゃあかんかな、俺これ観たかったんやけど」
時刻表から邦画のタイトルを指差すが、ひとみはそれも頷かなかった。
「洋画の字幕にしてください」
窓口でもたもたしていると後ろに並んでいる客が露骨に苛立ちはじめた。すぐ後ろのカップルは問答の内容が聞こえたのか「混んでるだから早くしろよな」「彼女のほうワガママー」などと聞こえよがしに嫌味を言いはじめたが、ひとみは一向に気にした様子はない。
伸行のほうがいたたまれなくなって、結局適当な洋画に決めた。「字幕なら何でもええんやね」とちょっとトゲのある確認をしてしまう。
入場がもう始まっていたので、お互いにトイレに行ってから慌ただしく館内に入り、あまり言葉も交わさないまま予告が始まった。
映画は封切り直後に少しCMが流れたきり話題にもならなかったB級アクションで、平坦な展開にあくびを噛み殺した。
ひとみのほうを窺うとひとみもあまり面白そうではなく、これなら自分が主張した邦画のほうがよっぽど評判もよくて面白そうだったのにと内心で不満が湧いた。
スタッフロールが始まるや客が我先に席を立つような出来で「面白かったね」などと話が盛り上がるわけもなく、観終わってからの空気はかなり微妙だった。
せめて洋画を譲らなかったひとみが楽しんでくれていたらまだ救われるが、ひとみも席を立ってからあまり口を開こうとしなかった。伸行が気を遣って話しかけても、返ってくるのは無難な相槌や頷きだけである。(中略)
もうお開きにしたほうがよさそうですね、とおずおずとひとみが切り出す。
「せやね、雨も夜から酷くなるって天気予報で言ってたし」
やや言い訳混じりの投げやりな返事になったのはひとみにも伝わったのか、ひとみも寂しそうな申し訳なさそうな微妙な表情になった。
多分、本当はもっと話したかったのだろう。
「じゃ、ここ払ってきますね」
最初からそういう按分だ。ひとみが会計を終わらすのを店の外で待ちながら、次はあるかなと何となく考えた。微妙に気まずく終わったので、こちらから振らない以上ひとみからは会おうとは言いださないだろう。とすると今後の展開はひとまず伸行の掌中だ。
エレベーターを待っている間ひとみは何か物言いたげで、「あの」「すみません」と小さな声で繰り返していた。
「私、ホントは……」
やっとの思いでそう切り出したタイミングでぎゅう詰め下りのエレベーターが来て、ひとみは思い切れない様子のまま半ば機械的に開いた扉の中に乗り込んだ。
あ、無理ちゃうかそれ。
伸行が思った瞬間、重量オーバーのブザーが鳴った。だが、ひとみはまったく頓着した様子もなくそのまま乗り続けている。
さすがに元から乗っていた乗客の視線が険しくなり、伸行の我慢も在庫が切れた。
「おい、何ボサッとしてんねん!」
むしろ乗客に聞かせるために怒鳴りながら、ひとみの腕を摑んで引きずり降ろす。動作が多少手荒になったのはやむを得ない。
すみません、と頭を下げるが乗客たちはいくつかの舌打ちや白い視線を残して階下へ去った。
「何やってんや君も、」
余計な恥をかかされた苛立ちも手伝って声はきつくなった。
「自分の代わりに誰か降りろみたいなみっともない真似すんなや! 君がそんな奴やなんて思へんかったわ! ネットであんだけ感じよう見せといてリアルであんまりみっともない真似せんといてくれや!」
人の気配に聡い伸行には、今自分が周囲からどう見えているかも自覚されている。しかし今ひとみを責める言葉をこらえることはできず、ひとみが言い返さないことも相まって言い募ってしまう。
だが、言い返さない相手を一方的に詰るのも結局は後味が悪く、すぐに伸行の沸騰も収まった。
ずっと黙って伸行の口元を見つめていたひとみは、伸行が黙ってから口を開いた。
「……重量オーバーだったんですね」
おい、俺の話を聞いた結論はそこか!? 脱力しかけた伸行に、ひとみは深々と頭を下げた。
ここで、なぜひとみが伸行と会うことをかたくなに拒んだのか、その理由が明らかになります。それが、この物語の本当の始まりでした。そこから特別な二人の関係がスタートします。しかし作品のテーマは極めて普遍的です。それは、人の気持ちを思いやりつつ自分の気持ちを言葉にすることの難しさと大切さ、そして美しさとでも要約すればいいでしょうか。
解説の山本弘さんは『レインツリーの国』の感動を「鳥肌が立つほどの」という言葉で表現しています。作品を読めばこの言葉が誇張ではないことがきっとわかるはずです。