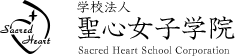フィールド日記
2013.06.17
ネジバナ ホタルブクロ ウツボグサ
2013.06.17 Monday
今日は「夏休み子供自然体験教室」の生徒スタッフのミーティングを行いました。下の写真は生徒スタッフに見せるために撮った自然観察コースの今朝の花々の写真です。百人一首にも出てくるネジバナ(1枚目)、昔子供が蛍を入れて遊んだというホタルブクロ(2枚目)、薬草としても有名なウツボ草(3枚目)などが咲いていました。8月にはどのように植生が変化しているか、今から楽しみです。



今日のことば
昨日の新聞から301 平成25年6月17日(月)
「人生」(『ピアノ協奏曲二十一番』(遠藤周作・文春文庫)所収)を読む
―― 人生に思いを馳せる読書 ――
6月14日に高校2年生の長崎祈りの会旅行について旅行会社の方と打ち合わせをする機会がありました。旅程をたどりながら話を進めていくうちに、長崎への思いが高まり、その日の夜は長崎のことをいろいろと考えて過ごしました。
旅程の中には遠藤周作文学館の見学が含まれています。金曜の夜に長崎のことを考えながら読んだものの中に、故遠藤周作の奥様が文学館への思いを記した言葉が引用されている新聞記事がありました。奥様は次のようにおっしゃっています。
遠藤がこんな字を書いていた、こんなものを使っていたということが、わかるだけの文学館になってほしくありません。あの土地にできた以上、殉教した人やころんだ人など、キリシタンに思いをはせる場所にしたい。そして、仕事に追われる日常を離れ、あの海を見て、人生や命について考える場所になってほしいと思います。
人生や命について、生命の終わりの時まで考えつくした遠藤周作の奥様ならではのお言葉と拝読しました。
その遠藤周作には、まさに「人生」と名付けられた小品があります。奥様の言葉を読んで、この作品を「昨日の新聞から」で紹介することを思いつきました。
「人生」は遠藤周作自身の体験が下敷きになっていると思われる作品です。満州で少年時代を過ごした遠藤周作は、満州の思い出を綴る形式で「人生」という小説を書きました。現地の人間をボーイとして雇ったことが語られる場面から最後までを引用してみます。
婆やが日本に去ってから、家にはお手伝いのかわりに満人のボーイが来た。
彼は毎朝、沢庵を売りにくる行商人だった。今、思うと年齢は十七、八歳だったかもしれない。母が家に住みこみで手伝わないかと言うと、即座に承諾して翌日から小さな手荷物ひとつ持ってやってきたそうである。
痩せて、いつも怯えたような表情をしたボーイだった。痩せているのは食べものにも困るような生活をしていたせいかもしれぬ。怯えた顔をしているのは彼が満人であるためかもしれぬ。そう言えば大連では日本人の巡査とすれちがうと、たいていの満人は卑屈な顔か、怯えた顔をさっとしたが、そんな表情がこのボーイの顔にいつもあらわれていた。
痩せて怯えたような顔をしていたが、それだけに彼は優しかった。特にずっと年下の私の面倒をよく見てくれた。
冬がきびしくなると、私たちのような小学生は登校が早い。一晩中、零度十度以上の寒さに曝された路はすっかり凍りつき、そこを歩くと尻もちをつくことがある。尻もちをつくのは小学生たちには楽しかったが、家から学校に行く途中にかなりの傾斜の坂があって、そこをおりるのは危険だった。
彼はいつもその坂の下までついてきてくれた。私が厚い外套を着て、襟巻を首にまき手袋をはめているのに、彼は父からもらった古いゴム長をはいているだけだった。私は今でも思いだす。彼が前にたってくれて、万一、私が滑った時、自分の体で支えようとしてくれた毎朝を。「キッケテ」とたびたび繰りかえしてくれた彼の不器用な日本語を。「キッケテ……ボッチャ、キッケテ」、それは坊ちゃん、気をつけて、の意味だった。
雪がつめたい風にまじって吹きつける時も彼は登校する私の前にたって壁になってくれた。吹雪のような雪片は彼の顔や体に容赦なく吹きつけたが、おかげで私はそれをまともに受けずにすんだ。
あの頃、少年の私はそれを当り前のことのように思っていた。彼が年上だから、家のボーイだから、当然の仕事だと考えていた。顔や腕にぶつかるつめたい風の痛さを彼がどんなに我慢していたかにも気がつかなかった。「キッケテ、ボッチャ、キッケテ」その声を思いだすと、今の私の胸は痛む。
冬が終わりかける頃、父と母との間が決定的に悪くなった。悪くなればなるほど私は学校で仮面をつけ、はしゃぎまわり、先生や友だちに暗い気持ちを見すかされまいとした。(中略)
ある日帰りが遅くなった。こんなに遅く帰れば心配した母からどんなに叱られるかを承知しながらもわざと帰宅を遅らせた。それは私の存在を無視して不和になっていく両親への反抗心からだったと思う。私は父と母とに仕返しをしたかったのだ。
(中略)
母にひどく叱られた。叱られても強情に私はあやまりもせず横を向いた。母は私をニ、三度、叩いた。すると隅で心配そうに見ていた彼が母のそばに寄って懸命に叫んだ。「オクサン、ヤメル。オクサン、ヤメル」彼は母に叩くのはやめろと訴えたのだった。
叩かれたことは反抗心をますます強めた。子供のかなしさをわかってくれない両親を恨めしく思うようになった。そして私は遅く帰校するよりも、もっとひどい仕返しを母にした。
それは母の大事にしていた指輪を盗んで売りとばしたことだった。彼女がその青い宝石のついた指輪をどこにしまっているか知っていたし、それを引出しから出すのは造作なかった。
盗んだあと、その指輪を学校に行く途中の満人の雑貨屋に持っていった。茶から一寸した満人の薬まで雑多に並べたその店では二人の男が指輪を電灯にかざして見たり、いじくりまわしたりした揚句、私に五十銭の銀貨を一枚くれた。
もらった銀貨で菓子を買い、そのつり銭を私は何処にかくそうかと迷った。子供心にも家のどこかにおけば、万が一、発覚した時、問いつめられるだろうと考えた。そして思案の結果、学校の校庭の隅に埋めた。
目じるしは校庭の庭に三本たっている高いポプラの樹だった。ポプラは秋になると黄色い葉をあたりに舞い落した。私たちはその枯葉をひろって、茎と茎とをたがいにからみあわせて引張り、切れた者を負けとする遊びをやった。
放課後、皆に見つからぬよう地面をほってつり銭の一部を出し、帰校の途中、買い食いをした。金はすぐなくなった。
半月ほどして母が指輪の紛失に気づいた。母は私の行為だとは思いもしなかった。そして疑いは満人のボーイである彼にむけられた。
「やはり満人だものね。いくら可愛がっても、こんなことをするんだわ」
と母は私に言った。
黙っていた。自分がやったと白状もしなかったかわりに、彼ではないのだと否定もしなかった。
翌日、町会長のような役をしているあの医者がオートバイにのってあらわれた。私は二人の会話をそばで聞いていた。
「警察につきだしたほうが、いいですよ、奥さん。満人にはやさしくしちゃ、駄目だ」
「でも……」と母は迷っていた。「まだ彼が盗んだという証拠もないし」
「だから警察できつく調べてもらうんですよ。そうすれば泥を吐きますよ」
二人の話を耳にしながら私ははじめて自分のやった行為が警察沙汰になるほど怖ろしいことだったと気づいた。胸がつぶれるような不安にかられた。どんことがあっても黙っていねばならぬとさえ思った。
医者は二時間ほど家にいると、ふたたびオートバイにまたがって帰っていった。遠ざかって行くオートバイの音は私の痛む胸にいつまでも残った。
母はもちろん彼を警察に訴えたりはしなかった。しかし翌日、学校から私が戻ると彼の姿はもう家にはみえなかった。もういないとわかりながら、私は彼が寝起きしていた台所の横の小部屋の前にたって、彼の名をむなしく二度、三度と呼んだ。怯えたようなその顔がいつまでも私の眼ぶたにちらついていた。
この年齢になると真夜中、ふと目のさめることが多い。眼をあけて自分の人生をかすめた人たちのことを思いだし、噛みしめ、恥しさと後悔のまじった気持に胸しめつけられ、呻きにも似たかすかな声を時にはあげることもある。たとえばあの満人のボーイのことを思いだすたび、私はその呻きにも似たかすかな声を口に出す……
昨年の秋、大きな船にのって四十年ぶりにその大連を再訪した。感無量だった。
四十七年ぶりで見る大連だが、街の外観はなにひとつと言って良いほど変わっていなかった。あたらしい建物はひとつも建てられていないかわり、昔のホテルはホテルに、公園は公園に、銀行は銀行に、学校は学校として使われていた。変わっているのは名称だけで、通りも広場も街路樹もすべて見憶えあるままだった。あの頃は広く大きくみえた建物も、五十七年も生きた大人の眼には低く狭くうつった。すべてのものが古ぼけ、すすけ、黒ずみ、同行した友人が思わず呟いた。
「まるでゴーストタウンだな」
しかし十月の空は鉛色でつめたかった。工場や人民公社を見ないかと奨める通訳をなだめながら私はかつて通った小学校と自分の住んでいた家とに連れていってもらった。
小学校は旅大市第九中学校という名になっていたが、校門も運動場もほとんど記憶のままである。先生たちに案内されて授業中の教室にも入れてもらった。ちょうど英語の時間で、生徒たちは女の教師に教わっていたが私たちが入ってもほとんどわき見をせずに黒板を注目していた。授業参観の客があっても眼をそらさぬように教育されていたのかもしれない。
(中略)
運動場には人影はなかった。運動場も昔のままだった。昔のまま向うに満鉄本社だった建物がみえ、長い塀がつづき、塀が終わってそこにポプラの樹がそびえていた。ポプラはあの時と同じように丈たかく、その数も三本のままである。そのポプラの根もとに私は母の指輪を売った金を埋め、素知らぬ顔をしたのだ。そしてそのあとに満人のボーイに罪をおしつけて知らぬ顔をしていたのだ。キツケテ、ボッチャ、キツケテ、ボッチャ。雪片が彼の寒さでゆがんだ顔に容赦なく当っていた……
もちろん先生たちはその時の私の表情に気がつかなかった。彼等は校門を出る私たちを拍手をしながら見送ってくれた。
これが「人生」という作品です。現代の私たちから考えると、極めて特殊な環境の特別な出来事ですが、何かここに、万人に理解できる「人生」の真実のようなものを感じないでしょうか。それは、敢えて言葉にしなくてもいい、それぞれがそれぞれの人生の体験の深まりのなかで感じ取っていけばよい何かなのではないかと思います。
9月に訪れる長崎の遠藤周作文学館での「人生や命について考える」時間を大切に過ごしたいと思います。