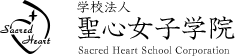フィールド日記
2013.01.25
マラソン大会 イワボタン
2013.01.25 Friday
今日はマラソン大会が行われました。コース終盤は裏道の坂道です。その厳しいコースを懸命に走っている生徒たちは実にいい表情をしていました。




生徒たちが走る裏道は、貴重な生物が数多く生息する道でもあります。下の写真はイワボタンです。裏道で最もよく見られる植物の一つです。佐賀県では絶滅危惧Ⅱ類に、鹿児島県では準絶滅危惧種に指定されています。イワボタンは湿地に生える植物ですが、裏道はいろいろなところで水が湧き出ていてイワボタンにとって適度な湿り気が土に含まれています。

今日のことば
昨日の新聞から35 平成17年4月18日(月)
曽野綾子の『二十一歳の父』を読む ―― ビタースウィートな青春 ――
4月10日の産経新聞に「ワンルームフォークの不思議」という記事が出ていました。次のような書き出しの記事です。
ドラマ「3年B組金八先生」挿入歌に使われ、問い合わせが殺到するなど話題を呼んだ「私をたどる物語」が、今月六日、シングルCDで発売された。作曲し、歌っているのはシンガー・ソングライター、熊木杏里(二三)。ドラマに主演する武田鉄矢が書いた歌詞に「曲をつけてみないか」と誘われ、武田が歌うことを前提に作ったら本人から「自分で歌ってごらん」と勧められた。
番組放映中から「問い合わせが殺到した」曲とはどのような曲なのだろうか。すぐに購入して聴いてみました。曲を伝えられないのは残念ですが、武田鉄矢の歌詞は次のようなものでした。
頬をぶたれた少年がひとり/日暮れの道で泣いている/父が憎いと声とがらせて/涙でゆがんだ空見てる
遠い未来が不安でならず/呼ばれて返事しなかった/だけどやっぱりきみが悪いよ/自分を隠しているからさ
さあ鉛筆しっかり握りしめ/私という字を書くのです/白いノートの私にだけは/夢を話してゆくのです
君しか書けないその物語/私という名の物語
髪を切られた少女がひとり/鏡の前で泣いている/母が嫌いと声をつまらせ/自分を悔しくにらんでる
ちがう親から生まれていたら/ちがう自分になれたという/だけどやっぱり/きみはちがうよ/そしたらきみはいなくなる
さあ鉛筆しっかり握りしめ/私という字を書くのです/白いノートの私とだけは/ずっと仲良くするのです
君しか書けないその物語/私という名の物語
なかなか味わい深い歌詞だと感じました。「自分探しの応援歌」とでも言える歌ではないかと思いました。自分を受け入れることをすすめ、自分らしく生きようとする人をあたたかく励ます歌だと僕は聴きました。
「さあ鉛筆しっかり握りしめ/私という字を書くのです」という歌詞を何度も聴いていて一つ思い出した小説がありました。
曽野綾子の『二十一歳の父』(新潮文庫)という小説です。(書店では入手困難。不二聖心の図書館には二冊あります。)これもまた主人公の酒匂基次という青年が自分らしく生きようとする姿に対して作者が温かいまなざしを向けている小説でした。この本とは、常盤新平の『ペイパーバック・ライフ』という本の中で次のような文章を読んだことがきっかけで出会いました。
『二十一歳の父』を文庫で読みかえしてみた。文庫の第一刷は昭和四十九年で、私の手もとにあるのは昭和五十四年九月五日発行の第十六刷である。五年間で十六刷ということは、一年に三回の増刷であって、このビタースウィートな青春小説のために、慶賀すべきことだ。私も最も初期の愛読者の一人としてうれしい。
私はじつに涙もろいほうで、いっしょに酒を飲んでいて、相手に「君、泣いちゃいけない」などと言いながら、先に涙をこぼしてしまうほうである。しかも、そのあとで酒癖が悪くなるから、翌日はもう布団をかぶって、恥かしさに耐えている。
しかし、『二十一歳の父』を雑誌で読んでいたころは、まだ下戸だったのに、たとえば、恋人の巌間恭子が、大学を卒業できるかどうかわからない、ただし生活力のある越秋穂に言う、なにげない言葉に胸が熱くなった。「たいていの人が生きているじゃない」と彼女は言うのである。そしてーーはい、私も生きています、と心のなかで呟いたおぼえがある。あのころ、私はそれほど涙もろくなかった。
十数年ぶりに『二十一歳の父』を再読しても、昔の印象は少しも変らなかった。いい小説だなあ。このひとことに尽きる。そのことに満足して、クリーネクスで鼻をかんだ。
それにしても、この私も変っていないと思った。三十歳のときと同じように、小説のおんなじ箇所で目と鼻が妙にゆるんでくるなんて、ちょっと情ないじゃないかとも思った。でも、この年齢で変身するのは無理だ。
常盤新平をして「いい小説だなあ。」と言わしむる小説がどんな小説なのか、さっそく買って読んでみましたが、期待に違わずすばらしい小説でした。
主人公の酒匂基次(さかわもとつぐ)は、エリートの家庭に生まれながら親と同じ道を歩もうとはせずに親の期待を裏切る人物として登場します。例えば父親が基次の通う大学の教授に次のように話す場面があります。
「私共では長男のほうは、まあまあ出来がよろしいのです。東大を出て、日銀に入りました。しかし次男はさんざんです。お世話になっておきながらそういうのもひどいものですが、実は入学の時もやっと入れて頂いたような状態でした」
酒匂は意味深長なものの言いかたをした。それからふと彼は長男の結婚式の日の嫁の姿を思い出した。白無垢を着て神々しいような花嫁であり、色なおしになって客をおくり出す時には、いっぱしのもの馴れたホステスぶりを見せた女である。嫁はW銀行頭取の娘でカトリック系の女子大学を出ている。語学もお料理も刺繍もみっちりと仕込まれていた。式は帝国ホテルで行われ仲人は広報社社長であった。立派な息子は、いい嫁をつかまえることが出来るという見本のような結婚式である。
その宴に、次男の基次は、髪も髭もぼうぼうの姿で現われた。式の前々日床屋へ行けと命じると、それ位なら兄さんの結婚式には出ない、と言い出した。其次はどちらかというと無口で不器用な子であったが、大学の演劇部に籍をおいて、映画のエキストラに出るために髪と髭を伸ばしているのだった。
「金がいるなら、その分だけ父さんがやるから、エキストラはやめて床屋へ行け」
酒匂はそう言ったが、其次はうんと言わなかった。
「何という映画だ?」
しまいには酒匂は息子に尋ねた。それは「敗走千里」という戦争ものの映画であった。舞台はフィリピンのジャングルが主である。
「だけど僕の出るのは違うんだ。夕陽を受けた砂浜に、見渡す限り死体が散らばってる、その死体になりに行くんです。やせて、髪や髭がのびている学生を募集しているんです」
酒匂は呆気にとられた。きいてみると、エキストラばかりではあるが、其次は実に今までに八本の映画に出演しているというのである。死体役になることにどうしてそう執着するのか酒匂はとても理解出来なかった。しかし、父子はいくらか言い合った挙句、結局、酒匂は折れることにした。
其次は乞食のような頭に学生服を着こんで結婚式に列席した。酒匂は男であったのでいざとなれば次男の髪のことなど気にもかけていなかったが、其次の叔母にあたる酒匂の妹は気にして、会う限りの人に其次の言訳ばかりしていた。
基次は大学を出てもろくな就職もせず、ついには最も親を落胆させる行動に出ることになります。ここからあとは話の筋を明らかにするのはやめましょう。自分自身で物語を読みながら、「鉛筆しっかり握りしめ/私という字を書」こうとした基次にとって本当の幸せとは何であったのか、そして私たちにとって真の幸福とは何であるのか、じっくりと考えてみてください。