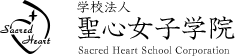フィールド日記
2013.01.24
1月のユズリハは特別です
2013.01.24 Thursday
縁起物のユズリハをあちこちでよく見かけた1月がまもなく終わろうとしています。不二聖心では聖心橋の手前でユズリハの木を見ることができます。1月が終わっても、親が子を健やかに育て家が代々続いていきますようにというユズリハに込められた思いを折々に思い出していきたいものです。

今日のことば
昨日の新聞から 87 平成19年1月22日(月)
『風と木の歌』(安房直子・偕成社文庫)を読む
―― さびしさは人の心を深くとらえ、落ちつかせるものなのだ ――
読売新聞の土曜日の夕刊に「名作ここが読みたい」という連載があります。各界の著名人が、思い出に残る名作を取りあげ、その中で最も印象に残る箇所を紹介します。
11月25五日(土)は、児童文学作家のあまんきみこが、安房直子の「だれも知らない時間」という作品を紹介していました。
まず、次のようなあらすじが載っています。
漁師の良太は、あと100年ほど命が残っているカメから毎晩1時間の時間をわけてもらい、夏祭りの太鼓の練習をしています。そこへ、昔やはりカメから時間をもらったという少女が来ました。少女はその時間を使って、海の上を走って島の病院に入院している母親に会いに行っていましたが、時間が切れて海の底へーーカメの夢の中へ落ちてしまったのでした。良太はカメに、少女を返してもらえないかと聞きました。
次にあまんきみこが最も心に残る箇所として挙げている部分の引用が続きます。
「でも、わたしも知らないんだ。いちど、夢の中にとじこめたものを、どうやってたすけだすのか。」
「ほ、ほんとかい。」
「ああ、わるいことしたね。」
良太は、目をまんまるくして、しばらくおそろしそうに、カメを見つめていましたが、やがて、にぎっていたこぶしをパラリとほどきました。それから、決心したように、こういったのです。
「そんならいっそおれも、おまえの夢の中にいれておくれ。百年間でられなくてもかまわない。あの子といっしょに、海の底でくらすよ。」
これをきくと、カメは、はじめて、ぱっちりと目をあけたのです。そして、良太をまっすぐに見つめると、しっかりした低い声で、こういいました。
「それはいけないね。元気なわかいものが、そんなことしちゃいけないね。」
「それじゃ、どうすればいいのさ。」
「やっぱり……わたしがなんとかしよう。」
「方法があるのかい。」
「ああ。たったひとつ。そう、夏まつりの晩までまっておくれ。」
「夏まつりまで?」
良太は、まつりまでの日にちをかぞえました。
「あと、ひい、ふう、みい、三日まつのかい。」
カメはうなずくと、ふとかなしそうな目をして、それから、ぽつりといいました。
「まつり晩はながいよ。」
それっきり、カメは首をひっこめて、良太がいくらよんでも、石のようにうごきませんでした。
(偕成社文庫『童話集 風と木の歌』207~208ページより)
そしてこのあとに、あまんきみこの文章が続くという構成になっています。続けて引用してみましょう。
安房直子さんが生きておられると、今、63歳。私は63歳の安房さんの作品を読みたい。50歳で永眠した安房さんが惜しまれてならない。天賦の才に恵まれた方だった。
「だれも知らない時間」は、初期の短編集『風と木の歌』に「きつねの窓」「鳥」「さんしょっ子」などとともにおさめられている。
このくだりは、老いたカメから毎晩1時間だけ時をゆずり受けた若者とそのカメの会話だ。だれも知らない不思議な時間に、太鼓のけいこを続けていた若者が、カメの夢に閉じこめられている少女を助けようとたのんでいる場面。「まつりの晩はながいよ」というカメの一言には深い意味がある。
実はこのあとも、あまんきみこの文章は続くのですが、これ以上引用すると話の結末がわかってしまうので、このあたりで引用をやめておきたいと思います。「まつり晩はながいよ」というカメの言葉にこめられた「深い意味」とは何なのか、実際に作品を読んで確かめてみてください。
この新聞の連載がきっかけで、僕は実に久しぶりに安房直子を読み直しました。十年以上、安房直子の作品は読んでいませんでしたが、今度読んでみて驚いたことは、二十代のときよりも作品がおもしろく感じられるということでした。『風と木の歌』に収められている短編はどれもすばらしく、最後に添えられた解説もまた読み応え充分でした。
解説を書いているのは蜂飼耳で、今まで読んだどの安房直子論よりも安房直子の作品の本質をよくとらえているように感じられました。一部、引用してみましょう。
安房直子の童話には特別な輝きがあります。それは、たとえばダイヤモンドのような、はではでしいきらめきではありません。むしろ、真珠やガーネットを思わせる、ひかえめだけれど、たしかな底光りを感じさせるような輝きです。
その童話のおもしろさは、おかしくて思わず声をたてて笑ってしまう、という性質のものではありません。そうではなく、ひたひたと心にせまってきて、本をとじたあとも、いつまでも体の底にずっしりと残りつづけるようなおもしろさなのです。(中略)
『風と木の歌』におさめられた八編の童話は、どれも体の底に響く深さをもっています。幸せ、悲しみ、じぶんの力ではどうにもできないものを受けいれること、信じること、うらぎること、うれしいこと、楽しいこと。生きていくことのすべてを抱きしめるようなこれらの童話にあるものは、なんだろうと、と考えます。いったい、なんだろう、と。それは、たぶん、勇気のようなものだと思います。じぶんの目の前でおきていることやじぶんがおかれている状況から目をそらさない勇気のようなもの。つらい、とか、いやだ、とか思うほんの少し手前で、目をそらさずに見つめる勇気のようなもの。大きな場面ではなく、むしろ小さな、見のがされてしまいがちな場面でこそ、見つめる力はしっかりとはたらくものなのかもしれません。
この童話集にはいっている作品のなかでわたしがもっとも好きなのは「きつねの窓」です。
この作品とであったのはたぶん、小学校の国語の教科書でのことだったと思います。国語の教科書などというと、なんだか、つまらないものの代名詞のようにきこえるかもしれません。学校も授業もたいして好きではない、おとなしい子どもだったわたしは、国語の時間も教科書のかたすみに落書きなどして、ぼんやりと空想にふけってばかりいました。
そんなある日のこと。国語の授業は「きつねの窓」へすすみました。読んで、びっくりしました。なんてさびしく、なんて美しい物語なんだろう、と胸をつかれた瞬間をそれから二十年たったいまもわすれません。
さびしいものより、明るく楽しいもののほうがいい、と受けとられがちな世の中かもしれませんが、そうとはかぎらないのです。さびしさは人の心を深くとらえ、落ちつかせるものなのだと知ったのは、もしかすると、この物語を読んだときだったかもしれません。(中略)
「さんしょっ子」「鳥」「だれも知らない時間」は、愛することの哀しみを描いています。愛する気もちというものは、ただ単にうちあければいいというものではありません。それは、ときにはじぶんの内側を破壊してしまうほど、深くからゆりおこされる感情の動きです。苦しくて避けたくなるような感情も作者は手にとって見つめています。その勇気が物語をいきいきと輝かせ、いつまでも体の底に残る響きをうみだしているのです。安房直子の童話は、作者がいなくなったいまも、ひっそりと静かに輝きつづけています。
幸いなことに不二聖心の図書館には『安房直子コレクション』(全6巻)がすべて入っていますので、安房直子の作品のほぼすべてを読むことができます。そして、このコレクションのうれしいところは、それぞれの巻末に安房直子のエッセイが少しずつ収められていることです。
これを機にエッセイをいくつか読み、安房直子さんという童話作家の人柄についても少し知ることができました。あるエッセイのなかで安房直子さんは、「私の作品は、どうか、なるべく、文学の教材として、あまり切りきざまずに、まるごと読まれてほしい」と言っています。ここからは、この願いを聞き入れて、あまり多くを語ることはやめ、僕の好きな「鳥」の最初のところをできるだけ長く引用して「昨日の新聞から87」を終わりたいと思います。
ある町に、耳のお医者さんがいました。
小さな診療所で、くる日も、くる日も、人の耳の中をのぞいていました。
とても、うでのよいお医者さんでしたから、待合室は、いつも満員でした。遠い村から、なん時間も列車にゆられてかよう人もありました。耳がきこえなくなりかけたのが、このお医者さんのおかげで、すっかりなおったという話は、かぞえきれません。
そんなふうで、毎日が、あんまりいそがしかったものですから、お医者さんは、このところ、すこし、つかれていました。
「わたしも、たまに、健康診断しなくちゃいけないな。」
夕方の診療室で、カルテの整理をしながら、お医者さんは、つぶやきました。いつも、看護婦役をしてくれるおくさんは、ついさっきでかけてしまい、いま、お医者さんは、たったひとりでした。夏の夕日が、その小さい白いへやを、あかあかとてらしていました。
と、ふいに、うしろのカーテンが、しゃらんとゆれて、かんだかい声がひびきました。
「せんせ、おおいそぎでおねがいします!」
耳のお医者さんは、くるりと、回転いすをまわしました。
カーテンのところに、少女がひとり立っていました。片方の耳をおさえて、髪をふりみだし、まるで、地のはてからでも走ってきたように、あらい息をしていました。
「どうしたの。いったい、どこからきたんだね。」
お医者さんは、あっけにとられてたずねました。
「海から。」
と、少女はこたえました。
「海から。ほう、バスにのって?」
「ううん、走って。走ってきての。」
「ほう。」
お医者さんは、ずりおちためがねをあげました。それから、
「まあ、かけなさい。」
と、目のまえのいすをしめしました。
少女は、まっさおな顔をしていました。その目は、大きく見ひらかれ、まるで、毒をのんでしまった子どものようでした。
「それで? どうしたの?」