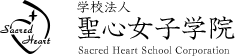フィールド日記
2013.02.17
フキノトウが顔を出しました

2013.02.17 Sunday
寒い一日でした。風も冷たく、黄瀬川の近くでジョウビタキを見かけたほかは、生き物の動く気配がほとんど感じられない一日でした。タゴガエルの鳴き声もまったく聞こえませんでした。かろうじて見つけた春の兆しが今日の写真です。今年も裏の駐車場の縁にフキノトウが顔を出しました。早春の山菜として古くから日本人に親しまれてきたフキノトウですが、その中にはフキノール酸、ケンフェノール、アルカロイドなどのポリフェノールが多く含まれ、胃を強くし腸の働きを整えるそうです。フキノトウを食品として利用することは極めて理にかなったことであったということです。
今日のことば
最近、大江邦夫『オディロン・ルドン 光を孕む種子』(みすず書房・二〇〇三年)という本を読んだ。フランスの画家、ルドンをめぐる本だが、そのなかで、とくに心に残ったのは、ルドンの若き日の友人であったアルマン・クラヴォーについての章だった。
クラヴォーは、植物学者。いつも顕微鏡を手もとに置き、生命の研究にはげんでいた人物。ルドンよりもひとまわり年上で、生物学のみならず、文学や思想などにも詳しく、貴重な本を集めて書庫をつくっていたという。ルドンは、画家となる前、まだ十代のころに、クラヴォーと出会い、深い影響を受けたとされている。インドの詩について聞かせるなど、ルドンの興味を引く魅力を秘めた人だったのだろう。ルドンはパリへ出て、絵の道を模索するようになる。一方、クラヴォーは、ボルドーで研究をつづける。けれど、その実力にもかかわらず、ボルドー植物園長の要職を与えられないなどの挫折があって、四十過ぎてから自殺してしまう。
いったい、クラヴォーは、どんな人だったのだろう。静かな部屋にいて熱心に顕微鏡をのぞきこむ男のすがたが浮かんでくる。あるいは、書庫の本棚から本を抜き取り、ゆっくりと開く男の背中が、浮かび上がる。
百年以上前の地方都市ボルドーで、インドの詩を愛読したり、神秘思想にも通じていたというクラヴォーは、理解と同時に、多くの誤解も受けていたにちがいない。孤独だったかもしれない。だが、私には、この人物のすがたは、幸せのひとつのかたちであるように見える。
研究を正当に評価されず、最後は自殺。その名も、歴史のなかに長く埋もれていた人物なのだ。それなのに、なんとなく、この人は幸せだったのではないだろうかと思える。どうして、そう感じるのだろうと考えて、とても単純な答えに辿り着く。つまり、この人は、なにをやりたいのか、いつも自覚していた、ということだ。
充実、などという言葉で表せば、あまりにも陳腐になってしまうけれど、一瞬一瞬が、内側からきっちりと支えられていた人ではないかと感じられる。自分の内側から支えられる、ということは、とても大事なことだと思う。
蜂飼耳