フィールド日記
2011.05.19
中村久子とハンショウヅルとアシナガバチ
平成23年5月19日 木曜日
今日の国語の授業で中村久子さんの「ある ある ある」という詩を生徒に紹介しました。中村久子さんは、
病のために3歳の時に両手両足を切断した女性で、ヘレン・ケラーをして、「私を世界の人は奇跡の人と言う
けれど、あなたこそ、真の奇跡の人」と言わしめた人物です。
「ある ある ある」は次のような詩です。
さわやかな秋の朝
「タオル取ってちょうだい」
「おーい」と答える良人がある
「ハーイ」という娘がおる
歯をみがく
義歯の取り外し かおを洗う
短いけれど指のない
まるいつよい手が 何でもしてくれる
断端に骨のない やわらかい腕もある
何でもしてくれる 短い手もある
ある ある ある
みんなある
さわやかな秋の朝
「ないないない」と言いがちな私たちに「あるもの」に目を向ける大切さを教えてくれる詩です。
自然の中にたたずむと自分の心が「あるあるある」という思いに満たされていきます。
5月10日に「不二聖心のフィールド日記」で紹介したハンショウヅルがようやく花を咲かせました。

5月15日に紹介したアシナガバチの女王蜂は今日も巣作りに励んでいました。
5月15に「フィールド日記」に掲載した写真と比較して少し巣が大きくなってきたように感じられます。
成功率3割の大家族作りへの挑戦はまだまだ続きます。

2011.05.18
高校3年生の短歌④とアブラギリ
平成23年5月18日 水曜日
高校3年生が最近詠んだ歌を紹介します。
思い出につい手が止まり一時間部屋の片づけ進まないまま
窓あけてやる気まんまんテスト勉強プリント飛ばされやる気消失
お弁当定番メニューのたまご焼き砂糖が多めの母の味
休み明け準備に練習・小テスト五月病にもかかる暇なし
あくびして悲しくないのに涙でるほんとは心が泣いてるのかな
もう少し勇気があれば伝えたいあなたに言えない私の気もち
アルバムを開いて微笑む父と母「大きくなったね」微笑む私
一日が長い長いといいながらふとふりかえるともう金曜日
窓開けて星空見つつ深呼吸夜を一息吸い込んだようだ
制服を衣替えしてふと思うこれで最後の夏服なんだ
みんながいてほんとによかった幸せですこんな友達一生出来ない
アブラギリの花が目につく季節となりました。アブラギリは不二聖心の中で不思議と数が多い樹木の一つです。
風の強い日に、大木のアブラギリから白い花がいくつも一斉に落下していく様子はなかなか壮観です。
アブラギリは、その実から油が採れることからアブラギリと名付けられましたが、別名イヌギリともいいます。
植物の世界では、「イヌ」という言葉はある種の 蔑称として付けられることの多い言葉ですが、
アブラギリの美しい白い花を見ていると、とてもイヌギリとは呼べないという思いになります。

2011.05.17
ホホジロアシナガゾウムシ
平成23年5月17日 火曜日
象に姿が似ているところから「ゾウムシ」と名付けられた昆虫がいます。ゾウムシは、日本には1000種以上、
世界には約6万種いると言われますが、 不二聖心にもかなりの数の種類のゾウムシが生息しているものと
考えられます。そのうちの1種が下の写真のホホジロアシナガゾウムシで、「温情の灯」の碑の 近くで
見つけました。ホホジロアシナガゾウムシは、ハゼやヌルデの木の枝を折って産卵します。ということは、
「温情の灯」の碑の近くに、ハゼかヌルデの木 が生えているはずだと推測できるわけです。
生き物のつながりから、実際に目にしていないものの存在を推測することも、自然観察の面白さの一つです。

2011.05.15
富士山とアシナガバチの営巣
平成23年5月15日 日曜日
今日は一日中、富士山がくっきりと見える五月晴れの一日でした。

今年初めてアシナガバチの営巣を確認しました。見つけたのは二か所で、一か所はニガイチゴの葉裏、
もう一か所はオナモミの枯れ茎でした。両方の巣で卵も確認できました。越冬した女王バチがたった
一匹で巣作りを始めましたが、ここから大家族を作り上 げることに成功するのは約3割と言われています。
今後も女王の巣作りを見守っていこうと思います。


2011.05.14
ヤツボシハムシの色彩変異
平成23年5月14日 土曜日
面白いものを見つけました。
下の写真に2匹のハムシのオスがメスを奪い合っている様子が写っています。2匹のオスは体色が全く
異なっていますが、種の異なるオスがメスを奪い合うこと はあり得ません。これはどうしたことかと
不思議に思って専門家の方に写真を見ていただいたところ驚くべきことがわかりました。
2匹のオスは同じヤツボシハ ムシだというのです。


ヤツボシハムシは下の写真にあるように8つの黒色紋があるためにヤツボシハムシと名付けられましたが、
時にその黒色紋が拡大したり縮小したりすることがあります。上の2匹のオスのうちの一方は黒色紋が拡大して
体全体を覆ってしまった例であり、もう 一方は黒色紋が薄くなってほとんど消滅しかけている例だったのです。
ここに掲載した3枚の写真はすべて不二聖心で撮影したものですが、限られた地域の一つの種の中に
これだけの色彩変異の多様性があることに驚きました。

2011.05.12
キンランとスダジイ
平成23年5月12日 木曜日
講堂の横の道で絶滅危惧種のキンランを見つけました。ここ数年、姿を消していたキンランが
よみがえったのです。
ところで、この写真に写っているキンランの横の木が何かわかるでしょうか。
植物のことがいろいろわかってくると、これだけの画像である程度の樹木の特定が 可能になります。
5月9日の「不二聖心のフィールド日記」に「キンランは菌根菌と共生関係にありますが、
菌根菌は栄養を特定の樹木から得ていると言われま す。つまり三者が共生関係にあるわけです。」と書きました。
つまり、「特定の樹木」とは何であるかを調べれば写真の樹木の見当もつくということです。
答え は「ブナ科に属する樹木」です。講堂の入り口近くにある樹木のプレートで確認してみたところ、
「ブナ科スダジイ」と書かれていました。
本来、キンランは雑木林でよく見られるランです。雑木林のクヌギやコナラと講堂横のスダジイは
だいぶ姿の異なる樹木ですが、それらが確かに同じ仲間であることをキンランは私たちに教えてくれます。
ちなみに、不二聖心の保護の聖人である聖ローズ・フィリピン・ドゥシェーンの「ドゥシェーン」は「かしの木」を意味しますが、その「かしの木」もまたブナ科に属しています。

2011.05.11
『兄のトランク』とアカメガシワ
平成23年5月11日 水曜日
昨日の中学校朝礼で山本校長先生が、宮沢賢治の弟、宮沢清六さんのお宅を訪問した時の思い出話をなさり、
宮沢清六さんの『兄のトランク』(ちくま文 庫)という本を紹介してくださいました。お話をうかがって
『兄のトランク』を懐かしく思い出し、昨晩久しぶりに読み返して、次のような一節に出会いまし た。
賢治の生まれた明治二十九年という年は、東北地方に種々の天災の多い年であった。(中略)この年の六月十五日には、三陸海岸に大津波が襲来し、最高 二十四メートルの高波が海岸の家屋を破壊し、二万一千人の死傷者を出した。その上、七月と九月には大風雨が続き、北上川が五メートルも増水、家屋、田畑の 損害も甚大であった。
そして夏になっても寒冷の日が続き、稲は稔らず赤痢や伝染病が流行した。
賢治が日清戦争の直後に、この周期的に天災の訪れる三陸海岸に近い寒冷な土地に生まれたことと、
彼が他人の災厄や不幸を常に自分自身のものと感じないでいられなかった善意に満ちた性格の持ち主であった
こととは、実に彼の生涯と作品とを決定する宿命であった。
宮沢賢治が2011年を生きていたら、今回の震災に何を思い、どう行動しただろうかと考えずにはいられません。
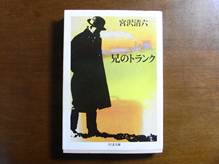
不二聖心の校舎の裏道では、アカメガシワの葉が成長を続け、名前の由来となった赤い色も徐々に目立た
なくなってきました。蜜腺が育って甘い蜜を出すように なり、たくさんのアリが集まってきています。
アカメガシワは災害や開発などで緑が失われた地にいち早く芽生え、森林の傷跡をふさぐと言われています。
津波で緑が失われた地でもあちらこちらでアカメガシワが芽生え、たくましく葉を茂らせていくことでしょう。

2011.05.10
アフリカ入門とハンショウヅル
平成23年5月10日 火曜日
昨日の中3梅組のホームルームで担任の下川真喜子先生が生徒に『日本人のためのアフリカ入門』
(白戸圭一・ちくま新書)という本を紹介なさいました。先生が引用したのは、次の箇所です。
確かにアフリカからは政治の混乱や貧困に耐えかねた多くの人が域外に流出していますが、圧倒的多数の人は生を受けた土地での暮らしを主体的に肯定 し、祖国で生涯を終えます。アフリカから「脱出」してアフリカ域外で暮らしている人々でさえも、祖国に誇りの念を抱き、アフリカの社会や文化に強い愛着を 抱いていることが一般的です。そこで私は考えました。私たちは、アフリカの人々のそうした気持ちに、どの程度思いを馳せたことがあるだろうか。少し踏み込 んで言うと、私たちは、アフリカの人々が少なくとも我々と同じ程度に祖国に誇りを持ち、我々と同じ程度に優秀で、我々と同じ程度に幸せな暮らしを営んでい ることを知っているだろうか。
日本とアフリカの経済規模や科学技術の水準の差に目を奪われ、国力の差を個々人の幸福度の違いと錯覚し、
「進んだ日本、遅れ たアフリカ」「幸せな日本の暮らし、気の毒なアフリカの暮らし」と思い込んではいないか。
アフリカを深く理解することを通してのみ、私たちは「幸せな日本の暮らし、気の毒なアフリカの暮らし」という型にはまった物の見方から自由になれるのでしょう。不二聖心での教育では、広く知ることとともに深くわかることを大切にしたいと考えています。
ハンショウヅルの蕾が徐々に大きくなってきました。ハンショウヅルは、2つの県で絶滅危惧種に指定されて
いる、ツル性の植物で、ぶらさがるようにし て咲く花の姿が半鐘に似ているところからハンショウヅルと名付けられました。その花は、蕾の時から紫色に覆われた姿が独特の美しさを持っています。実はこの蕾の外側は花弁ではなく、すべて萼片です。植物の中には萼片が一見したところあたかも花弁のように見える種類がかなりあります。ここにも一つ、じっと見 ることで「深くわかる」世界があります。

2011.05.09
高校3年生の短歌とキンラン
平成23年5月9日 月曜日
連休前に高校3年生が詠んだ短歌を紹介します。体育大会に向けての歌が増えてきました。
6年目こなくていいよと父に言う ふとふり向くとその父がいる
今年こそ4人の団長筆頭に狙うはトロフィー ファイナルチャンス
時間ない時間がないと嘆きつつ ちゃっかり見てる韓国ドラマ
ありがとう母の骨折れ気づかされる一人でこんなにしてたんだね
寄宿生高3の悩みはただ一つ 夕食の話題今日はどうしよう
毎年の居残りダンスつらいけど「今年で最後」に動き良くなる
イースター色とりどりのたまごたち もったいなくて食べられないの
きれいだな桜舞い散る4時間目それでも私は花より団子
ごめんねとその一言が言えなくてたかが一言されど一言
絆創膏傷口隠して見ないふり心の傷は隠せないまま
各色が協力している光景は勝ち負けなんて関係ないな
ほろ苦い甘さひかえめこの味が青春の味ビターチョコ
新緑の若葉が萌える窓の外 心も豊かに決意も新たに
今年も雑木林でキンランが見られる季節になりました。かつて雑木林で普通に見られたキンランは、今では
41の県で絶滅危惧種に指定されるようになってしま いました。キンランは菌根菌と共生関係にありますが、
菌根菌は栄養を特定の樹木から得ていると言われます。つまり三者が共生関係にあるわけです。
三者が共 存できる不二聖心の雑木林だからこそ生きられるランであり、不二聖心のフィールドの「共生」の
シンボルと言えます。

2011.05.08
ワラビとヤマトシリアゲムシ
平成23年5月8日 日曜日
今日の不二聖心は初夏の陽気が戻り、イカルやウグイスが風薫る五月の空に鳴き声を響かせていました。
4月14日の「フィールド日記」に中学1年生のワラビ採り体験の授業のことを書きましたが、
5月に入ってワラビはすっかり成長し若々しい葉を広げています。
今日はワラビの葉の上でヤマトシリアゲムシがとまっている姿を何度も見かけました。
ヤマトシリアゲムシは名前の通り、尻を上げて葉の上にとまる珍しい昆虫 です。気に入ったメスにオスが
エサをプレゼントして機嫌をとるという生態も非常にユニークです。この行動は「求愛給餌」と呼ばれます。

ワラビの葉には特殊な酵素が含まれるために、その葉を食べることのできる生き物は限定されてしまうのですが、今日はカクモンヒトリとワラビハバチと思われる幼虫がワラビの葉を食べていました。

他にも何種類かの生き物がワラビの葉を求めてやってきていましたが、
その訪問者を狙うカニグモ科のクモも目撃しました。

フィールドを歩いた時間はごく短時間でしたが、それでもこれだけの生き物と出会うことができました。
今度は「ワラビとつながる生き物探し」というテーマで授業をしたらきっとすばらしい授業ができると思います。

















